2025年4月27日放送の「がっちりマンデー」で注目を集めた岩手県のナンバーワン企業「薬王堂」。人口わずか5,000人ほどの過疎地域でも成功を収める独自のビジネスモデルが話題になっています。一般的なドラッグストアとは一線を画す薬王堂の戦略と、西郷孝一社長が語る「働かないことで売り上げが上がる」という驚きの経営哲学から、地方創生のヒントを探ってみましょう。
薬王堂が岩手県No.1企業になった理由とは?〜がっちりマンデーで話題に〜
2025年4月27日にTBS系で放送された「がっちりマンデー!!」では、「うちの県のNo.1会社!」という企画が取り上げられました。各都道府県に本社があり、最も売上高が大きい企業を紹介する内容です。加藤浩次さん(極楽とんぼ)と進藤晶子さんがMCを務め、経済アナリストの森永康平さんやテツandトモさんがゲストとして出演していました。
この番組内で岩手県のナンバーワン企業として紹介されたのが「薬王堂」です。年間売上高が1,500億円を誇るこの企業は、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、岩手県では圧倒的な存在感を示しています。なぜ薬王堂が岩手県でこれほどまでに成功を収めることができたのか、その理由に番組は迫りました。
薬王堂の会社概要と東北地方における展開戦略
薬王堂は東北6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)に集中して店舗展開するドラッグストアチェーンで、現在約405店舗を運営しています。創業は今から47年前の1978年に遡り、西郷孝一氏の母親が薬剤師で岩手出身であったことから、岩手県で薬局を開業したのが始まりでした。1982年に薬だけでなく生活必需品も扱う「薬王堂1号店」を出店し、そこから東北地方を中心に着実に店舗数を増やしてきました。
薬王堂の特徴は、東北6県という限られたエリアに集中出店する戦略を取っていることです。全国展開よりも、特定地域でのドミナント戦略(一定地域に集中して出店する戦略)を採用することで、物流コストの削減や地域ニーズへの的確な対応を実現しています。
人口7,000人でも出店できる薬王堂の独自ビジネスモデル
薬王堂の最大の特徴は、その独自の出店戦略にあります。一般的なドラッグストアチェーンは、店舗を出す際、半径1kmから2kmの範囲内に1万人以上の人口がいることを目安にしています。しかし、薬王堂はこの常識を覆し、商圏人口が7,000人程度でも出店可能なビジネスモデルを確立しました。
これは岩手県をはじめとする東北地方の人口分布を考えると、非常に理にかなった戦略と言えます。人口密度が低い地域では、従来の基準に従うと出店できる場所が限られてしまいます。そこで薬王堂は、他のチェーン店が出店しないような人口の少ない地域にも積極的に店舗を展開することで、競合のない環境で商圏を確保しているのです。
岩手県葛巻町の事例から見る成功の秘訣
番組では、この戦略の具体例として岩手県葛巻町の事例が紹介されました。葛巻町は盛岡市から車で約1時間半、人口わずか5,300人ほどの小さな町です。一般的な小売チェーンなら出店を躊躇するような場所ですが、薬王堂はここに葛巻店を出店しました。
驚くべきことに、この葛巻店は薬王堂の全400店舗中、売上高で上位40店舗に入る好成績を上げています。なぜこのような過疎地域でも高い売上を達成できるのでしょうか。その秘密は地域住民の買い物行動にありました。
一般的なドラッグストアとの違い〜なぜ田舎でも儲かるのか〜
薬王堂が人口の少ない地域でも高い収益を上げられる理由の一つは、豊富な品揃えにあります。一般的なドラッグストアとは異なり、薬王堂の店内には医薬品や日用品だけでなく、食品、衣料品、ペット用品など、生活に必要なものがほぼすべて揃っています。
葛巻町の住民へのインタビューでは、「食品もあるし、薬も買えるし、日用品も買えるし。大体ここ来れば揃う感じ」という声が聞かれました。これまでは町外に出て買い物をしていた住民が、薬王堂ができたことで町内で買い物を済ませられるようになったのです。
この「なんでも揃う」という特徴が、来店頻度の増加につながっています。人口が5,000人でも、週に3回来店してもらえれば延べ15,000人の来客数になるという考え方です。実際、葛巻町の住民は「週に1〜3回は来る」と話しており、この戦略が成功していることがわかります。
薬王堂が実践するローコストオペレーションの内容
人口の少ない地域で収益を上げるためには、売上高だけでなく、コスト管理も重要です。薬王堂は徹底したローコストオペレーションを実践することで、人口の少ない地域でも利益を確保しています。
経済アナリストの森永康平氏は番組内で、「徹底的にローコストオペレーションで回すと。で、売り上げがそこまで立たなくてもちゃんと利益ができる体制というのは一つ」と指摘しています。
具体的なローコストオペレーションの内容については、西郷社長自身が「無駄な仕事はやめていく」ことにこだわってきたと語っています。小売業界では一般的に長時間労働や複雑な作業が多いとされますが、薬王堂ではそうした常識を見直し、効率的な店舗運営を実現しているのです。
西郷孝一社長が語る「働かないことで売り上げが上がる」経営哲学
「がっちりマンデー」の中で西郷孝一社長は、独自の経営哲学として「働かないことで売り上げが上がる小売業を作りたい」と語っています。これは単に労働時間を減らすということではなく、無駄な作業を徹底的に排除し、本当に必要な業務だけに集中するという考え方です。
西郷社長によれば、小売業界は「働かせすぎ」の傾向があるといいます。長時間の接客や商品整理、棚卸しなど、従来当たり前とされていた業務を見直し、本当に顧客満足につながる業務に集中することで、効率的な店舗運営を実現しています。
この哲学は、地方の過疎地域で店舗を運営する上で特に重要です。人口が少なく、従業員の確保も難しい地域では、一人当たりの生産性を高めることが不可欠だからです。
少子高齢化時代における地方ドラッグストア経営の可能性
薬王堂の成功は、日本の将来を先取りしたビジネスモデルとも言えます。森永康平氏が番組内で指摘したように、「東北地方はその少子高齢化の人口減少が全国的に進んでる地域なので。これって実は日本の将来像じゃないですか。どこもそのうちそうなるよねと」という状況です。
現在、日本全国で少子高齢化と人口減少が進行しています。今後はますます地方の過疎化が進み、薬王堂が直面しているような状況が全国的に広がっていくでしょう。そのため、多くの小売業者が薬王堂のビジネスモデルを「日本の将来のあり方」として参考にしているというのです。
過疎地域でも収益を上げられるビジネスモデルの確立は、地方創生にも大きく貢献しています。地方の住民にとって、生活必需品を購入できる場所が近くにあるということは、生活の質を大きく向上させるからです。
まとめ:薬王堂の成功から学ぶ地方創生ビジネスのヒント
岩手県No.1企業の薬王堂が実践する「人口過疎地でも儲かる」ビジネスモデルは、他のドラッグストアチェーンや小売業にとって多くの示唆に富んでいます。その成功の秘訣は以下の3点にまとめられるでしょう。
- 人口が少ない地域でも、豊富な品揃えで来店頻度を高めることで売上を確保
- 徹底したローコストオペレーションで、売上が少なくても利益を出せる体制を構築
- 「働かないことで売り上げが上がる」という効率重視の経営哲学の実践
これらの戦略は、単に薬王堂の成功事例として興味深いだけでなく、今後の日本社会全体が直面する課題への解決策としても注目されています。少子高齢化と人口減少が進む日本において、地方の活性化は大きな課題です。薬王堂のような地域に根ざしたビジネスモデルが、その解決の一助となることが期待されます。
「がっちりマンデー」で紹介されたこの事例は、単なる成功企業の紹介にとどまらず、日本の将来を考える上でも貴重な視点を提供してくれています。
※ 本記事は、2025年4月27日放送(TBS系)の人気番組「がっちりマンデー!!」を参照しています。
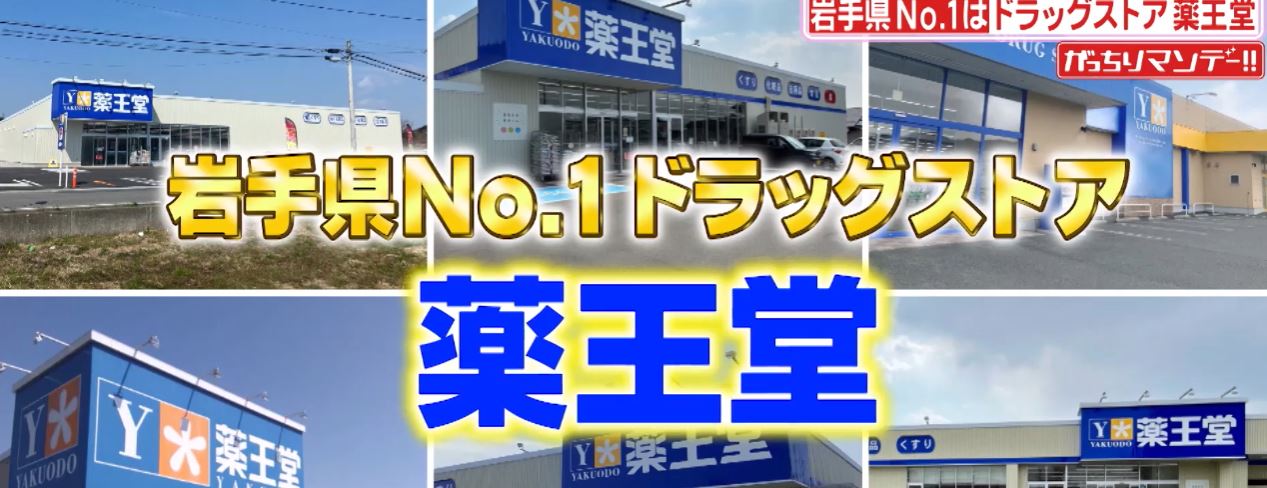


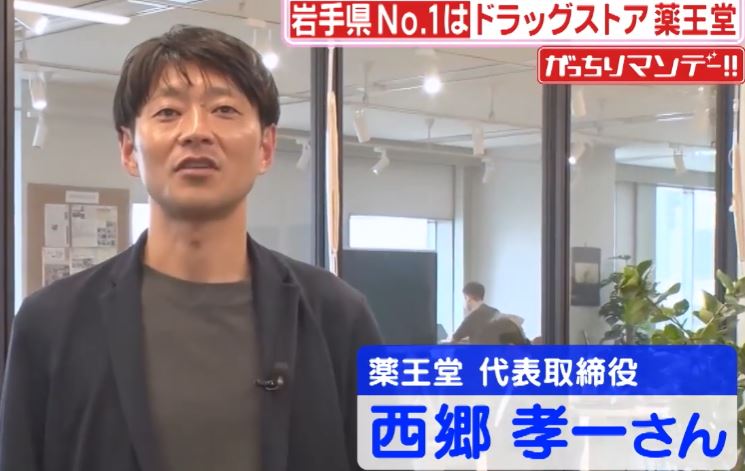


コメント